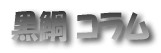|
- 石井さんはず〜っとがまかつ派なんですか? -
石井「いえ、そういう訳ではなかったんですけど、最近はそうですね」
- 昔の竿で印象に残っているのは? -
石井「D社初代トーナメント磯とか良かったですね・・」
- 私はレイダムが出た当時からがまかつを使い、途中BBXとかDAIWAの飛竜とか、インナーまで手を出しましたが
やっぱり最近では外ガイドに落ち着いてきたようです -
石井「結局外ガイドを使いますね、私は、ULガイドの方が好きです。
今使っているレイダム1.0号0.8号はわざわざULに交換しています。
ただし、強度に難があるので、1年で新品のガイドに交換します」
- グレ競技SP2なんかもULでしたね、私はULは傷つきやすいししまう時固まりやすいので・・苦手なんですが -
などなど・・話はどんどんそっちの方向に・・・・・・・
メーカー的な話はあまり突っ込んで書けないので、今回は割愛。
-------------------
中略
-------------------
-いよいよ本題ですが、30年間ずぅ〜っと黒鯛一筋だったんですか? -
石井「いや、最初は20歳の頃からヘラブナ、そして海ではメジナ釣りでしたかねぇ・・
その後は石鯛を3年ほどやりましたか」
- へら?ですか。 黒鯛師の方に”へら”やってる人は多いですね -
石井「ええ、相模湖とか大きいの出るでしょ、ですからそれはそれで魅力があったんですよ、
尺上も結構上げましたね、あの頃は」
- 相模湖ではやはりナイター・・ですか? -
石井「昼、釣ってましたね」
- 房総といえば三島湖をはじめとして結構へらの釣り場がたくさんありますよね?
私は家が多摩川近くなので、本流もやったし、相模川の砂利穴も良く出かけていました。
その当時は発砲のロング浮きが流行って、多摩川の本流では皆使っていましたね。
・・おっと、話がそれてしまいました、黒鯛に戻りましょう(笑) -
石井「まぁ、浮きが立ち浮きだし、あたりとかの感覚が共通するものがありますから当然でしょうね」
- メジナ釣りは? -
石井「当時オキアミが解禁になったでしょ、そしたら良く釣れましたね、新島でも大型の入れ食いに会いましたし、
初島でもゴロタで40オーバーの入れ食いも経験しました」
- 確かに、あの頃は黒鯛もたくさん釣れましたが、メジナの釣れ方は半端じゃなかったみたいですね。
西伊豆とかにはは行かれなかったんですか? -
石井「行きましたよ、いろいろ」
-メジナは釣れ過ぎて飽きちゃった・・という事かな?(笑) それで石鯛釣りに移行していったという事ですか -
石井「まあ、磯釣りと言えば当時は石鯛ですからね、そうでしたよね」
- 磯釣りのガイドブックや雑誌も石物の記事がメインでした。
今では幻の魚とか言われていますが、石鯛歴を聞かせて下さい -
石井「石鯛は20代の後半頃から3年程続けましたかねぇ、それで離島も通ったわけですが、
結局3年で10枚、最大は56cm4キロでした」
- 今で考えるとなかなか達成の難しい数字ですね、それで石鯛から黒鯛に移られたきっかけは? -
石井「結局、石鯛釣りは場所もそうだし、体力がかなり必要なんですよ、それでややキツくなってきて、
近場で大きいのが釣れる可能性のある黒鯛に変わって行ったんです」
- 約20数年前・・ということですね -
石井「そうですね、たまたまその頃”新宿クロダイクラブ”のN氏と知り合って、
それから外房のS釣具に通い始めたんですよ、当時、N氏が店を出しましたから・・
それで、南房浮きとかを使って暫くは内房で無く、あのあたりを攻めていました」
- 最初に釣った黒鯛って覚えていますか? -
石井「確か吉浦の堤防で、自作のバルサ電気浮きで夜釣りました。1.6キロありましたか」
- それは黒鯛を始めてどのくらい経ってからの事ですか? -
石井「2年近くはオデコ続きでしたから・・・・」
- なるほど、石井さんでも苦労されたんですね初物は・・それまで石鯛、メジナ、へらのスキルを持ってしても・・ -
石井「そうでしたね、ですから黒鯛が釣れるようになってからメジナとへらはやらなくなりました。
やっぱり黒鯛は簡単に釣れるものじゃないですからね・・」
- 確かに・・・たまたま大型が釣れてしまう事がある・・ところがコンスタントには釣れない
だから確実に釣る様にする為には、幾つかのステップを踏破しなければならない。 -
石井「ですね」
- そのへんのステップ・・という所が初心者の方やなかなか釣れない人の参考になれば・・ -
石井「まず、魚のいる場所、季節、気象条件、・・・これらがある程度備わっていれば
つれる確率は割と高いと言えるでしょう。
したがって、技云々・・と言うより、こちらの方が重要だと思いますね、
ですから如何にして魚のいる場所を知り、海洋気象を解析する事ができるようになるか・・・・
当然それには釣行回数も重要ですし、伴って経験値も上がりますからね」
- そう簡単には潮を見たりできないし、ポイントの絞りも最初は難しいですよね・・それにはどうしたら? -
石井「やはり知っている人に連れて行ってもらうのが最善でしょう。
- 石井さんは全てご自分で探索されていったんですか?-
石井「そうでもないですね、最初は話したとおりS店のN氏、そして今の田口会長の房総黒研・・
やはり人から聞いたり、教えてもらう事は大切だと思います」
- 雑誌、まぁ、ある意味ではメディア全体・・勿論このクロパラもそうですが、
情報は反面教師となる・・・・と、いうより本来の姿で情報は出てきませんね
ですから、私が黒鯛を始めた当初は自分のホームグラウンドで食わなくなった時、
結局は雑誌のガイド、釣行レポートに頼らざるを得なかった。
だからガイドに”黒鯛が出る”とか書いてあると季節如何に関わらず闇雲に出かけて行った
それこそ銚子から西伊豆まで、踏破しました -
石井「それで結局釣れないんですよねぇ」
- そんなもんですね、おかげでそれ以来情報を整理する能力みたいなものが身につきましたが・・
ところで、石井さんが房総黒研に入られたきっかけは? -
石井「浮きに惚れた・・・という事ですね」
- たぐち浮きですね? -
石井「勿論浮きの選択は人それぞれですが、当時有名なT浮き、そしてK_T浮き、
今は無き五洋の頃のT氏等の使っていた浮き。
内房は立ち浮きの宝庫でした、しかしその中でも自分はこの浮きが気に入りました。
まぁ、どちらかと言えば近場、中距離用の浮きですが・・・・まぁ、浮きは形状、感度より使い勝手優先でいいと思いますよ」
- 成る程、それで房総黒研に入られてから変わった事とかありますか? -
石井「まず沖磯や離島には行かなくなりましたね、と言うのは内〜南房総の堤防、地磯周りで
十分に釣れるからです、風が変わったら場所変えもすぐ出来るし・・小回りが効くと言う事ですね。
房総はどんな風でも何処かしかで竿が出せますから」
- それで現在は副会長でいらっしゃいますが、今までの記録とか、簡単に教えて下さいー
石井「ここ17年間で、会の中のルールに基づいた年間順位があるんですが、
3位、3位と続いた後、2,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,2,3,3位・・・・と、いった成績です。
しかしこの頃は・・・年齢的に釣行回数が減っています。いい訳ですが(笑)
一番釣った時が叉長で*年間12m80cm、これは会ではまだ破られていません。
*注その週の最大魚一匹だけの叉長の年間合計
打率では年間55回釣行中、52回釣れた・・・52/55ですか・・3回のオデコのうち、2回チンタは釣っていますから、
その年釣れなかったのは赤潮の日、それ一度きりでした。
だいたい平均して6〜7割、いい時は9割の確率で釣っていますね」
- 毎週末、良い条件に当たる筈もありませんからね・・52/55!!それは驚きです -
石井「これも会では破られてませんね」
- もう破る事は出来ないんじゃ?? -
石井「まぁ、季節ごとに釣れる場所はありますから、読みを外さないようにすれば・・」
- おそらく初心者・・というか一般の黒鯛釣り師でもどうしてそれほど釣るのか・・知りたいんじゃないですか?
石井さん的にアドバイスのようなものがありましたら聞かせて頂きたいんですがー
石井「そうですね、まず上手な人から教えてもらうのが早道です。
例えば勝山近くのある場所なんか夜明けしか食わない・・
また、ある場所は南西で白っぽい濁りが入らないと釣れない。
通いなれて上手な人はこの辺の引き出しが多いんですよ、見極めも早いし。
条件が合うのかどうか・・これを一人で知るには長い時間が必要ですからね。
結局、皆あれこれ悩んだりしていますが、黒鯛は釣れる場所で釣れば釣れますよ、数の差は出ますがね・・・
なるべく根でも何でも潮表を狙うのが良いですね、多分裏では食わないと思います。
数を釣るにはある程度コマセは多いほうがいいし、底が砂地の場合は団子状にして5,6個まとめて沈める。
私は通常、一日バッカン2杯計24キロ程使います。余る事が多いですけど。
コマセのメリハリも必要です。これらは技、経験の部類と言えるかもしれませんが。
そしてアイテムとしてはやはり浮きが最重要ですね。」
- 当然根性とか粘り・・・これも必要ですよね -
石井「若い頃は金耀の夜から竿を出して、日曜の朝マズメまでやることもありましたが、
最近は歳のせい?か、あと一日、例えば明日はきっと釣れる!・・と判っていても帰っちゃいます」
- そのへんの粘りは確かに私も無くなってしまいました・・・体力はマストですかね・・やっぱり -
ちなみに、過去、時間帯別の釣果はどうですか? -
石井「だいたいですが、8割位は夜明け〜朝までに釣っていますね、水温15℃を境にして朝マズメが有利と考えます
また、時間帯ではないですが外房は荒れてる最中ず〜と釣れますが、
内房は荒れ始めが良く、荒れ続いてる2日目なんかは良くない・・・・・・どうしてでしょうね?」
- 仕掛けのベーシックはどんなものを -
石井「内房の堤防、地磯ですとそんなに取り込みに苦労する場所はありませんから、
私はS社のフォースの1.5号、これで一年中です。バラすことはまず無いですね。
道糸は毎週50m程ですが交換しています。
針はG社のチヌ2号・・これもほとんど変わりません、但し付け餌は各種持参します」
-オキアミだけではダメですか? -
石井「オキアミは飽食しているのか?解りませんがボケジャコ、袋イソメは持参します」
-やはり砂地の多い内房ならではの食性ですね
石井さんは季節ごと、どの辺りに行かれるんですか?これは見ている人が一番知りたいんじゃぁ(笑) -
石井「そうですね・・例外はありますが毎年冬場の1〜3月は館山付近に、
4〜6月は船形〜保田付近まで・・・この時期は一番割れますね、条件次第で。
そして夏は南房の千倉〜布良
10月から年末は館山〜保田・・と、いったところでしょうか?金谷は混むのであまり行きません」
-そうですね、確かに混む場所は釣れている事が多いですが、
黒鯛は静かに釣る魚だと言う事を忘れてはいけないと思います-
2002年度春季kuropara例会にて(後列左から4番目が石井氏)

- それでは最後に・・・・石井さんの釣行時の昼食は? -
石井「バナナ二本です」
- 今日はどうもありがとうございました -
2002春 くらげ仙人 記
|